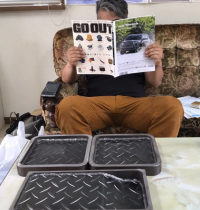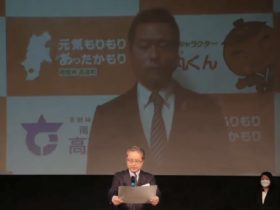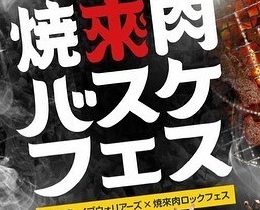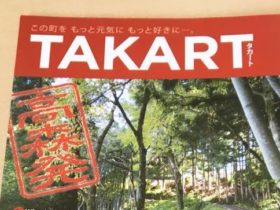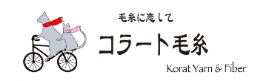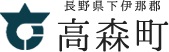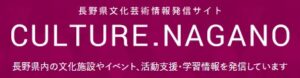- Home
- 高森町野鳥観察日記
高森町野鳥観察日記

2025.5.5 曇

ヤマザクラ
だいぶ残り少なくなってきたヤマザクラ。

オオルリ 2025.5.5撮影 高森町(900m)
もう、どんなに渋い日でもオオルリだけは撮れるってくらい、ありがたい鳥。鳥自体はそこそこ撮れてるけど、周辺がダメな写真しか撮れない日でした。
珍しく、ミソサザイの声がしない日。あちこちでキセキレイを見たけど、やっぱり上手く撮れず。
2025.5.4 晴

コハコベ? 直径5mmくらいの小さい花
鳥も花も、ちゃんと名前がある。知らんのがほとんどだけど。

ミソサザイ 2025.5.4撮影 高森町(1000m)
もっと近くて明るいチャンスがあったけどファインダーに上手に収められず。
今日は他に、上空を飛び交うサンショウクイ、遠くの梢で囀るオオルリ、姿は見えないセンダイムシクイ。相変わらず後ろ姿のカケス、まだ撮り方が分からないキセキレイ。ソウシチョウも声だけ。
2025.5.2 曇

ヤマザクラ
個体差はあるけど、だいぶ高いところの桜も盛りを過ぎたものが多くなってきました。予報では朝から雨予報で、5時過ぎには少し降っていたのですが、ちょっとだけでも様子を見に行きたいと思って出かけたら幸運続きで、結局2時間しっかり鳥撮り。

オオルリ 2025.5.2撮影 高森町(900m)
オスが2羽は珍しいシーン。幸運に感謝。

ソウシチョウ 2025.5.2撮影 高森町(1160m)
ミソサザイが囀っている藪の中にレンズを向けたら、じゃなくてソウシチョウ。こっちに気を撮られてミソサザイは撮り逃がしたけど、ソウシチョウも久しぶり2回目のご対面で幸運でした。

オオルリ 2025.521撮影 高森町(1160m)
今季一番近めで撮れた。ツバメと一緒で天気が悪いから虫が低いところを飛ぶのでオオルリも低めに陣取るってこと?
2025.5.1 晴

無名の滝
不動滝の少し下に美しい三段の滝があります。今まで見えなかったこの滝は、周囲の木が整備されたことで見えるようになりました。この角度からの滝つぼの前に立ちはだかる朽木、切っちゃいたい。
5月に入って明るくなるのが早くて嬉しい。今日も700m付近が面白くて、キビタキは聞こえなかったし、撮れない鳥もいたけど、キセキレイやヤマガラが撮れたし、オオルリの行動範囲もまた観察できた。あ、あとカワガラス。

キセキレイ 2025.5.1撮影 高森町(700m)
ハクセキレイとセグロセキレイはちゃんと解像した写真が撮れたことあるのですが、キセキレイはいつも失敗。これも解像してない。

ヤマガラ 2025.5.1撮影 高森町(700m)
大好きな芋虫類が少ない季節を生き抜いて、この季節が嬉しそう。カラ類にはもっともっと昆虫類を食べてほしいです。うちの庭の木もカミキリムシ入ってますよ。カラ様のお越しをお待ちしております。

オオルリ 2025.5.1撮影 高森町(900m)
今年はこの木がお気に入りかぁ。顔は見えなかったけど、発色がきれいに撮れたので。
900mから1000m地点へ向かう途中に現れる黒い鳥、今日も撮れなかった・・・。
2025.4.30 晴

ウワズミザクラ
手がかじかむほど寒かった今朝は標高700m付近が熱かった。やっと撮れたキビタキと、撮れなかったけど近かったオオルリ、謎の鳥と、サンショウクイ。

キビタキ 2025.4.30撮影 高森町(700m)
あー思い出してきた。キビタキと言えばこの角度とこの暗さ。そうそう。今季は何回明るいところで撮らせてもらえるかなー。

サンショウクイ 2025.4.30撮影 高森町(700m)
写真撮るにはまだちょっと暗い。サンショウクイは飛びながらピリリって鳴くから、見かけると言えば見かけるけど、なかなか止まってくれないから写真が少ないです。

オオルリ 2025.4.30撮影 高森町(900m)
今日はオオルリを700m, 900m, 1000m, 1200mの4地点で目視できました。

謎の鳥 2025.4.30撮影 高森町(700m)
これは700m地点で見た、たぶんコサメビタキ?分かりません。
今日は他にカケス、ミソサザイ、ヒヨドリ、謎の黒い鳥(たぶんクロツグミかな)を目視できました。
2025.4.29 晴

ブルーベリー
早朝は標高900m付近へ。今日のオオルリはそれほど高くない枝の密集したところを移動。水平距離で直径200mくらいの範囲を動いているように見える。遠くの鳥を撮る練習的な写真しか撮れなかったけど、オオルリの行動範囲が分かった気がする。

ミソサザイ 2025.4.29撮影 高森町(1000m)
夕方、ちょっと時間ができたので、ワンチャン鳥撮りへ。高森町の山は陽が沈むのが早くて、夕方の写真はあまり期待できないけど、ミソッチが相手してくれた。ミソサザイは行動範囲の直径100mくらいなイメージ。

ミソサザイ 2025.4.29撮影 高森町(1000m)
暗いところで撮るとノイズが多くなると言われますが、このザラザラ感、むしろ好きで。
2025.4.28 曇

ヤマブキ
早朝から中央道のBOXにイワツバメの様子を見に行ったんですけど、やっぱり、どこをどうすれば撮れるのか見当もつきません。BOXの中は暗いし、外出てくれば飛び回ってるだけで電線で休憩もない。採食は飛びながらだし。
諦めて山へ行く途中で池にカルガモ1羽。1羽ってめずらしい。
700m付近で、すっげー遠くの針葉樹の樹頂にいるオオルリを見つける。キビタキは聞こえない。840m地点は静か。900m地点でミソサザイとセンダイムシクイとオオルリ、クロツグミが聞こえる。オオルリが比較的低めのところを動いているようなので、今日はこのオオルリに時間いっぱいまで執着してみた。

オオルリ 2025.4.28撮影 高森町(900m)
樹頂だと空バックで黒くなっちゃうので、低めのところで山バックがありがたい。

オオルリ 2025.4.28撮影 高森町(900m)
条件はそんなに良くなかったけど。
2025.4.27 晴

ヤマザクラ
6時半頃から、ここ数日のお決まりコースへ。ヤマザクラは今が見頃です。700m付近で遠くからオオルリの声が聞こえたけど、遠すぎてスルー。キビタキは聞こえなかったっすね。840m付近、時間帯が違うせいかウグイスもセンダイムシクイも聞こえず、そのまま900m地点へ。ミソサザイ、オオルリ、センダイムシクイが聞こえる。目の前5mくらいの木に突然ミソサザイが現れたけど、フォーカスが合う前に移動していきました。焦ったー。

ミソサザイ 2025.4.27撮影 高森町(1000m)
移動するミソサザイの囀りの後をついて行くと、なんやかんや100mくらい移動。そして隣のミソサザイのテリトリーに接したらしく、近い距離で2羽が鳴き比べ。それにしてもミソサザイ、目の前に現れてあらためて小さい!。ピンポン玉くらいです。この体であの音量、イメージしづらい。

コガラ 2025.4.27撮影 高森町(1000m)
ミソサザイを離れて元の位置に戻ると、お久しぶりのコガラがキブシの花なのか、花についた虫なのかを食べにきてました。

オオルリ 2025.4.27撮影 高森町(1000m)
今日のオオルリはずっと高いところから高いところへの移動ばかり。

クロツグミ 2025.4.27撮影 高森町(1000m)
初対面はクロツグミ。複雑なさえずりを繰り出す様子が見られて幸福度が上がりました。
8時半くらいになると、一帯の鳥の声がおさまったので撤収。なんて気持ちのいい日曜のスタート。やっぱり、濃い場所で待つ鳥撮りが楽しい。

何の木だか分からないけど、なかなか洒落た新芽。
2025.4.26 晴

八重ヤマブキ
今日も5時半から。キビタキの声がするあたりをしつこく探して見たけど姿が見えない。

オオルリ 2025.4.26撮影 高森町(900m)
インスタにオオルリの投稿が増えてきたけど、どうやってあんなドラマチックなシーン撮れるのか。この後1000m付近でもオオルリいたけど高過ぎるところで黒いシルエットだけ。低いところに降りてきてくれないかと、しばらく待ってみたけど、どっか飛んでってしまいました。

カケス 2025.4.26撮影 高森町(900m)
オオルリが飛んでっちゃった直後に、いつもは飛び去る姿しか見せてくれないカケスがちょっとの間だけ相手してくれました。

カワラヒワ 2025.4.26撮影 高森町(700m)
肉眼ではモズに見えたけど、レンズ向けてみたらカワラヒワっぽくないような、とは言えカワラヒワだった。
センダイムシクイも何度か聞いたけど、見えそうで見えなかった。昨日と同じポイントでミソサザイが聞こえるんだけどこれも見えそうで見えない。
高森の山は朝が明るいから撮りやすい。夕方は野鳥が活発になる時間帯には暗くなってしまうのであんまり条件が良くない。
2025.4.25 曇
5時半から約1時間の探鳥。まずは標高700m付近で今季初、大好きなキビタキの囀り。姿は見えなくてもちゃんと嬉しい。
去年も聞き覚えがある囀りなのに鳥の名前が出てこない鳥の多いこと。気になるわ~。

カワガラス 2025.4.25撮影 高森町(700m)
この辺では、流れの上を飛ぶ様子を見るくらいだったので、撮影は初めて。ガードレールの隙間からけっこう見下ろす感じ。
右からはオオルリが聞こえ、左からはキビタキが聞こえ、川にはカワガラスっていう幸せなポイントでした。

エナガ 2025.4.25撮影 高森町(900m)
センダイムシクイの声が響く中でエナガが3羽ほど採食中。

センダイムシクイ 2025.4.25撮影 高森町(900m)
高木の梢の辺を転々とするので、今日のセンダイムシクイは真下からド逆光の条件ばっかり。

オオルリ 2025.4.25撮影 高森町(900m)
今日も遠いし高い。通っていればいつかは低いところにも来てくれるよね。これで距離65mくらい。
2025.4.24 曇
今朝の探鳥散歩は1枚も撮れず。でも、山で朝から鳥のさえずりに耳を澄ます時間はいい。声だけならセンダイムシクイ、ウグイス、ヒヨドリ、ミソサザイ、オオルリ、シジュウカラ、ヤマガラ。一瞬の飛んでる姿はカワガラス、ミソサザイ、カケス。
中央道のボックスに通っているイワツバメを撮ろうと出向いたけど、あんな速くて止まらない鳥をどうやって撮るんだろう。手がなくすごすご帰ってきましたが、帰りに道路際でコジュケイ。今日唯一の釣果が超久しぶりのコジュケイでとても嬉しい。
それと数日前からツツドリが聞こえてる。

コジュケイ 2025.4.24撮影 高森町(700m)
久しぶり。ペアでいたけどメスは撮れなかった> <
2025.4.23 雨-曇
一日中雨予報だったけど、夕方近くに雨があがった。天竜川で探鳥。

コチドリ 2025.4.23撮影 高森町(400m)
天竜川って、もっといろんな鳥がいるって聞くけど、自分ではあんまり見かけない。だし、中洲って地味に遠くて、羽毛がまぁまぁ解像しない。

ムクドリ 2025.4.23撮影 高森町(400m)
全然珍しくない、そこいらにおる鳥だけど、町内で撮ったのは案外初めて。

ツグミ 2025.4.23撮影 高森町(400m)
4月に入って、ちょっと出会う率があがってきているツグミ。果樹園の辺にもけっこういるし、たまには庭にもやってくる。
今日は他にコガモ、セグロセキレイ、カワウ、ダイサギ、ヒヨドリ、ホオジロを目視。
2025.4.22 曇
鳥撮り始めてもうじき1年、聞いたことのない囀りがいろいろ聞こえてきてワクワクします。

無事、冬を越えてくれたナガノパープル
暖かくなってきましたが早朝はさっむい。ワークマンで見つけたポンチョが風防にちょうどよくて嬉しかった。ミソサザイは2羽、目の前を横切りました。カケスも2羽、飛び去る後ろ姿だけ。

ウグイス 2025.4.22撮影 高森町(840m)
今日のセンダイムシクイは声だけ。姿を見せて撮影の相手をしてくれたのは今日もウグイス。ありがたい。

オオルリ 2025.4.22撮影 高森町(1000m)
今季初オオルリ。3日前に囀りが聞こえた気がしたのは900m付近、今日は1000m付近まで登って出会えました。見つけたところで鳥撮りの時間切れ、今朝は予報より暗いし、ま、初日はこんなとこでヨシとしときましょう。
2025.4.21 晴

月 2025.4.21撮影

ウグイス 2025.4.21撮影 高森町(840m)
センダイムシクイを撮りたい一心で昨日と同じ場所へ。6時頃、昨日と同じ木で姿を見るも、写真には至らず。ここ、ウグイスが撮れるおかげでウグイスの挙動が見えてきた。カワガラスとミソサザイとヒヨドリを目視。
2025.4.20 雲

オニグルミの芽
4月後半、いろんな木が芽吹いています。朝5時30分、松島さんの情報を元に標高840m付近で車を停めるとすぐにセンダイムシクイの声がしました。

センダイムシクイ 2025.4.20撮影 高森町(840m)
声はするけど姿が見えないという状態で40分ほど待ったら50mくらいむこうの枝にちょこまかと動くセンダイムシクイを発見。絵にはならないけど大満足の記録写真。松島さんありがとうございます。かわいいし、なんだろ、ウグイスよりウグイス色のイメージに近い。

ウグイス 2025.4.20撮影 高森町(840m)
そうこうしていると、ん?、ウグイスの声が近づいてきている。声が聞こえる方向とは一致しない場所で囀るウグイスを発見。沢いっぱいに響く声なので、どんな高いところで囀っているのかと思いがちですが、実は地面の際の藪の中で囀っています。
撮れるまで何年かかるだろうって思っていたウグイスが撮れてすげーラッキー。噂には聞いていたけど、地味だし藪の中だし、でも全身の形を変えるほど音を共鳴させて鳴く様はさすが日本三鳴鳥。
2025.4.19 晴ー雲

だいぶ気温が高くなってきたので夏鳥がやってきそうな予感がして、いてもたってもいられません。

ノスリ 2025.4.19撮影(480m)
メガドンキに買い物行く途中、田沢川沿いに東に向かう、トビより少し小さい猛禽類発見。朝霧の里の辺で上昇気流を捕まえた様子。白地に黒い斑、腹巻模様、ずんぐりした胴体、ノスリっすね。

ルリタテハ 2025.4.19撮影(1,000m)
夏鳥を探しに、少し標高の高いところへ。オオルリの囀りっぽいものが聞こえてたと思うのですが姿をみつけることはできませんでした。そんなに遠くなかったし、目立つところにとまる鳥なので、聞き違いか、いや、オオルリだったなー。ずっと高い木の梢を眺めていたのですが、ふと目の前にルリタテハ。全然希少じゃないんですけど、意識して見ないっすよね、なかなか。

ルリタテハ 2025.4.19撮影(1,000m)
羽根を閉じると岩か樹皮みたいな色ですが、開くと青っぽい綺麗な模様になってるんです。松島さんに聞いたら、この時期に見られるルリタテハは越冬した個体らしくて、羽根が傷んでるものが多いそうです。そしてルリタテハがとまっているこれ、キブシっていう雌雄異株の落葉低木なんですって。蜜を吸っているようでした。あと、それにしても、鳥待ちに蝶撮りがちな件ね。
あとミソサザイ、カケスは姿を見ただけで撮れず。
大島山ではツグミ。ウグイスが近くてもしやと粘ったけど全然見えず、ガビチョウもかなり近かったけど声だけ。頭の上をオオタカが飛んでいきました。
自宅にイカルがやってきて囀ってましたが顔は見せてくれず。松島さん情報ではセンダイムシクイの囀りを確認できたそうです。まだ自分が見たことも聞いたこともない野鳥、探しに行ってよう、や~でもムシクイ系は撮りづらい印象あるなー。コジュケイが近くで鳴いてるけど、見えないなーこれは。
2025.4.18 曇
1,000m付近の川沿いへ出かけると、移動中ずっとミソサザイが元気。まー基本的に姿は見えないんだけど、1羽だけ不意に目の前を通過。移動中のミソサザイはカメラで追えるもんじゃないです。明日はもっと上まで行ってみるかな。なお、オオルリはまだ来ていない模様。
あーずっとノスリの声が聞こえてるな。撮りいきたい・・・。
2025.4.17 晴

2025.4.17撮影 高森町
ハーモニックロードより上の桜はまだまだこれからが盛り。ウグイスはそこらべったりで聞こえるけど見えないよなー。コジュケイも元気な声聞こえるけど、散歩がてらの探鳥じゃ、まぁお目にかかれない。あ、撮れなかったけどアオゲラがいました。初めて。

メジロ 2025.4.17撮影 高森町(700m)
遠いけど桜とメジロ撮れて、なんかほっとした。

ツグミ 2025.4.17撮影 高森町(700m)
東京ではあんなに近くに来てくれたツグミも、高森ではしっかり距離おかれる。
や~、カモフラのポンチョでも買うかなマジで。

アオサギ 2025.4.17撮影 高森町(660m)
ここでよく見かけるいつものアオサギと色が違う気がするけど、季節的なものなのかな。普通に別の個体か。
2025.4.16 晴

お祭りやら何やらで久しぶりの探鳥は早朝の1時間。池でカワウとコガモとツバメ、モズ、キジバト。

カワウ 2025.4.16撮影 高森町(570m)
この池は満水時と比べて水位が2mほど下げたまま。去年の夏はカワセミをよく見かけたけど今はカワウしかいない。

ヤマガラ 2025.4.16撮影 高森町(660m)
あまり桜の花と関連がないような気がするヤマガラだけど、人生初の桜と野鳥撮れた。

ヒヨドリ 2025.4.16撮影 高森町(660m)
写真の出来うんぬんより、桜と野鳥が撮れた嬉しさが大きい。咲いてるうちに来れて良かった。メジロはいたけど撮れなんだなー。イカルとホオジロの囀りが聞こえる。
1時間で町内を巡回しようとすると、1か所の滞在時間が短いのが惜しい。
2025.4.10 曇ー雨
飯田美博の市民ギャラリーで、写真展「~輝き~」開催中です。黒木奈津子さんと櫻井ふじ子さん、お二人の写真が展示されています。野鳥と花の写真展です。今週末の13日までが会期となっています。
撮れん。鳥撮り始めて11カ月、こんな写真1枚も撮れたことがない。すげぇ。構図とか光線とかもちろん素敵なんですけど、そもそも前提としてキッチリ解像できているってところがもう、下手くそな自分からしたら、すでに凄くて。

2025.4.9 快晴
この春初めて不動滝行ってみた。シジュウカラ、キセキレイ、カワガラス撮って、ミソサザイとカケスが声のみ。吉田古城は撮れなかったけどメジロとシロハラとヒヨドリ。瑠璃寺も撮れなかったけどメジロ。

仙丈ケ岳 2025.4.9撮影 吉田古城

ヤマガラ 2025.4.9撮影 高森町(700m)
数日でも撮れない日が続くと、こんな角度からのヤマガラでも嬉しい。
桜にメジロとか撮ってみたいよ。

シジュウカラ 2025.4.9撮影 高森町(1,200m)
久しぶりに、ちょっと標高の高いところに行ってみた。同じシジュウカラでも庭で撮るのと山で撮るのとじゃ喜びが違う。

キセキレイ 2025.4.9撮影 高森町(1,200m)
春になると黄色が鮮やかになるときいたことがあるキセキレイ。確かに、そんな気もする。巣作り始めたんですね。
2025.4.8 晴
ウグイスが春だなぁ。鳥撮りを始めるまでは、自分がウグイスを見たことがないことにさえ気づいていなかった。聞こえるけど見えないウグイス。まだシロハラが聞こえる。ジョウビタキはいなくなったかな。池には若いアオサギ。ツバメ増えたな。

牛牧神社の桜 2025.4.8撮影
今年はお祭りと桜のタイミングがばっちり。天気がちょっとね。
2025.4.6 雨
昨夜のキャンドルナイトはそこそこの人出でした。

キャンドルナイト 2025.4.5撮影 高森南小学校

日本一の学校桜 2025.4.5撮影 高森南小学校
満開までにはもう少し日数が要りそうです。

ハクセキレイ 2025.4.5撮影 高森町(530m)
キャンドルナイト翌朝のゴミ拾いは、もっといろいろおるかと思ったけど。
桜にメジロとか撮ってみたいよ。

ヒヨドリ 2025.4.5撮影 高森町(530m)
花の蜜ならいくら吸ってもいいでな。
2025.4.4 晴
明日のキャンドルナイト、桜が間に合わないか~。吉田古城の桜まつりは来週だけど、「高森古城桜」も遅めだからなー。
そろそろルリビタキも探しに行きたい。もう来てるんじゃないかな

仙丈ケ岳 2025.4.4撮影 高森町

カワウ 2025.4.4撮影 高森町(660m)
通りすがりにいつもの池。今日はアオサギもカルガモもカワセミもいない。ここでは初めてのカワウ。
2025.4.3 雨ー曇
風景撮りにいくくらいの時間しかないので鳥撮れないなー。梅とか桜にメジロが集まるのかと思いきや、いない。まだ早いのか?撮れるのは家から見えるヒヨドリだけ。ヒヨドリ、キャベツ食い散らかすみたいで農家からの評判悪いっすね~。

ヒヨドリ 2025.4.3撮影 高森町(700m)
曇りの夕方に羽ばたいている様子を止めようと1/3200くらいにするとノイズが多くてあまり好ましくないって言われるけど、このジャリっとした感じ、嫌いじゃないんすよね。
2025.3.30 晴
今日は萩山神社と白髭神社で春のお祭り。晴れてはいるものの、風も強いし寒い1日でした。
いつもの池にアオサギ。庭にツグミがやってくるようになりました。地面に虫が出来たんでしょう。ジョウビタキはまだそこらを飛び回っています。
2025.3.28 曇
今日、天竜峡でソメイヨシノが咲いたそうです。野底山自然公園で焼來肉ロックフェス2025の記者会見があったので、遊びに行きがてら5分ほどカメラを持ち出した程度ですがコゲラいました。

コゲラ 2025.3.28撮影 野底山森林公園
この木は穴だらけ。

キチョウ 2025.3.28撮影 野底山森林公園
もう蝶がいましたよ。

ルリタテハ 2025.3.28撮影 野底山森林公園
これからは蝶を撮るのも楽しそう。


野底山森林公園の管理棟にこんなお知らせがありました。

シジュウカラ 2025.3.28撮影 高森町(700m)
家に戻り、庭先でシジュウカラ。
2025.3.27 曇
今日は豊丘の山が見える程度の黄砂で、曇りでも暖かい1日。ここ数日、なかなか鳥撮りに出かけられない。早朝5時30分頃になると聞いたことのない声が聞こえてきてソワソワします。
21日に奄美大島を出て25日に四国入りしたサシバは現在、大阪や奈良で動きを止めているそうです。

ヒヨドリ 2025.3.27撮影 高森町(400m)
どんな花に顔をつっこんだんだろ。
2025.3.26 曇
黄砂で遠景が見えないうえに風が強い。池のアオサギは光線がいい感じだったけど撮影は飛ばれそうだったのでスルー。車運転してても、ホオジロとカワラヒワくらいしかすれ違わなかった、あ、ツバメいた。ちょっと早過ぎないかと思ったけど確かにツバメ、池の上で虫を追ってた。
探鳥ポイントがまた変わってきた気がする。どこで何を待とうか。それはそうとこんな黄砂が濃い環境でカメラを長時間曝したくないなんても思う。
2025.3.25 曇
黄砂で豊丘村が見えない、もちろん南アルプスも。今日は探鳥に出かけられなかったけど、カケスが庭に降りてきて、部屋の中からだけど近くで見れた。カメラ持って庭に出るまで待ってくれる鳥じゃないもんなー。
21日に奄美大島を発ったGPSサシバは今日四国入りしたそうです。
2025.3.23 快晴
今日は町内各地で様々な催しがあった日でした。町内各地区の先頭を切って春季例祭を行ったのは吉田区。大島山瑠璃寺では薬師猫神様縁日、山吹ほたるパークではサッカーのソサイチ。

スズメ 2025.3.23撮影 高森町(400m)
天竜川にはホシハジロ、マガモ、カワアイサ、カワウ、ホオジロ、セグロセキレイ。天竜川近くの桜はだいぶ蕾が大きく赤く色づいていました。上段地区の桜はまだまだです。
今夜はジョウビタキが車庫にいない。暖かい日はできるだけ外で寝るとか?
2025.3.22 晴
まだ庭でジョウビタキの声がすると思ったら、まだいた。ただ車庫に帰ってこなくなっただけで、まだ庭で餌探してた。と思いきや、今夜は車庫にいた。いろいろ都合があるらしい。
GPS付のサシバが昨日、奄美大島を発った模様。
2025.3.20 晴

今朝は朝霧が出ていましたね。今日の塩見岳は頭が雲の上。

エナガ 2025.3.20撮影 高森町(840m)
ヒタキ類が姿を消して寂しくなった探鳥ポイントに、エナガとシジュウカラの混群、しかもシジュウカラ率が高い。ん?こんなときって・・・。

ミヤマホオジロ 2025.3.20撮影 高森町(840m)
出た!ミヤマホオジロがまた遠い!
やっぱりまた雪の後。

家の車庫で寝泊りしていたジョビオがとうとう今夜は帰ってこなかった。昼は庭の辺をちょろちょろしてたのに。何も言わずに行っちまった。あんな小さい体で海渡ってチベットまで行くやつもいるらしい。元気でな。
2025.3.19 雪-曇

昨夜からの雪で除雪車が出動した様子。飯田市でノスリの死骸から鳥インフル検出だって。一昨日は長野市でオオタカ。オオタカはともかく、ノスリが他の鳥を襲うシーンはみかけないけどね。鳥インフルで死んだカモでも食べたのか?
昨日、思いがけずイソヒヨドリが撮れて、なんか気分がいい。今日は山側が不調だったので天竜川で、ホオジロ、カワアイサ、マガモ、アオサギ、カラス、カワウ、セグロセキレイ。撮ったのはセグロだけ。ジョウビタキの声が聞こえてた気がする。

ハクセキレイ 2025.3.19撮影 高森町(400m)
ほぼいるし、ほぼ逃げないありがたい鳥、セキレイ。都会で暮らしたことがあるみたいなね。

ハクセキレイ 2025.3.19撮影 高森町(400m)
しかも今日は飛翔撮影の練習にも回かつきあってくれた。
2025.3.18 晴

だいぶ暖かくなってきたけど、今朝はちょっと冷えて霜がおりた。ルリビタキがいなくなった標高800m付近の林、今日はエナガ、シジュウカラ、ホオジロ、カシラダカ。ミソサザイの囀りが響いてました。ん~、ジョウビタキのメスも気配がない。

ヒヨドリ 2025.3.18撮影 高森町(700m)
何の木だか知らないけど、芽がどんどん大きくなってる。今日はシジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、カワラヒワ、トビ。

メジロ 2025.3.18撮影 高森町(700m)
野鳥の中で、メジロのこのきれいな緑色は独特だ。小さくてかわいいから、カラ類の混群に混じってるときはうれしいな。いやヤマガラやシジュウカラも嬉しいけど。
番外編 飯田市
午後から用事があって飯田市に。天竜川の岩場で元気に動き回る鳥影、カワガラスかと思いつつカメラを向けると・・・。

イソヒヨドリ 2025.3.18撮影 飯田市(400m)
え!? イソヒヨドリ。
「飯田市 イソヒヨドリ」で検索すると、2020年に飯田市で確認されているらしい。へ~
セキレイを追い払いながら、けっこう長いこと岩場付近を飛び回っていました。
長野県内だと1985年には佐久で、2010年には軽井沢で確認されてるって。
イソヒヨドリって名前のわりに内陸でも繁殖してるみたい。ま、それ言ったらイソシギもそうか。
いや~カメラ手放せない。

イソシギ 2025.3.18撮影 飯田市(400m)
イソヒヨドリが去ると、そのイソシギがやってきました。イソシギはだいたい遠いし止まらないので、自分の腕ではちゃんと撮れない。

カワウ 2025.3.18撮影 飯田市(400m)
婚姻色のカワウ。
他にはイソヒヨドリのスペースに入っては追われるを繰り返すセグロセキレイ、マガモのペアがいました。
2025.3.17 雪-曇

ホームセンターで買い物ついでにくるっと一周。アオサギ、カルガモ、マガモ、コガモ、カワウ、タヒバリ、セキレイ、ジョウビタキ、モズ、ホオジロ。うん、ルリビタキいない。

アオサギ 2025.3.17撮影 高森町(660m)
いるいる。そっと撮ってそっと帰ります。

タヒバリ 2025.3.17撮影 高森町(400m)
2回目の登場のタヒバリ。ほぼ茶色いセキレイ。

ヤマガラ 2025.3.17撮影 高森町(700m)
だいぶ夕方。
ルリビタキの気配が消えた?ジョウビタキはまだいる、ていうかオスだけ見る。
2025.3.16 雪-雨
今日は探鳥というより、用事があって出かけたときに見かけたって程度。カルガモ、カシラダカ、カワラヒワ、ジョウビタキ、シジュウカラ、ヤマガラ、ヒヨドリ、カケス、トビ。

ジョウビタキ 2025.3.16撮影 高森町(660m)
ジョビが高い電線に止まって遠くを見ていると、なんか北に出発する時期が近づいてるのかなって、勝手に想像して寂しい気持ちになります。

カシラダカ 2025.3.16撮影 高森町(660m)
鳥撮り1年目の冬を楽しませてもらったカシラダカ。
2025.3.15 雪
天気が良くなかったけど、家の周囲を少し歩いてみて。

カシラダカ 2025.3.15撮影 高森町(700m)
なぜか最近は探さなくても向こうから近づいてきてくれるカシラダカ。

ツグミ 2025.3.15撮影 高森町(700m)
高森町内では初見のツグミ。ちょっと大きいホオジロみたいに見えたけど、撮ってみたら。
2025.3.14 曇

昨日の夕方はアルプスと月が撮れるチャンスだったけど曇りが過ぎて月は見えなかった。アルプスは見えているけど、背景は空じゃなくて薄い雲。
ん~、ルリビタキを見なくなった、気がする。
池でいつものアオサギを確認、小川でいつものカワガラス、農耕地でメジロ、藪でカシラダカと久しぶりのベニマシコ。
シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラの混群は目視だけ。ミソサザイは複数の鳴き比べが聞こえました。

カワガラス 2025.3.14撮影 高森町(660m)
今朝は待ち時間無しですんなりカワガラス。カワガラスは瞼が真っ白。苔集めも一段落したのか、けっこうのんびりしてましたね。ここお気に入りの場所なんでしょうね。足元の苔が踏み均されちゃって。

ベニマシコ 2025.3.14撮影 高森町(660m)
久しぶりのベニマシコ。3月後半に入って、まだ高森町に滞在してくれてるんですねぇ。生息域を荒らしたくなかったので、あまり追ってなかったんです。

カシラダカ 2025.3.14撮影 高森町(660m)
最近は藪ばかりじゃなく、こうして枝にとまっているところに出会うカシラダカ。

メジロ 2025.3.14撮影 高森町(700m)
メジロも今までは地鳴きでしたが、今日は元気に囀ってました。けっこう複雑できれいなメロディだったの、知らなかった。
去年、桜とメジロとかの一般的な季節を過ぎた5月から鳥撮り始めて、夏の青々とした茂みに遮られて、メジロをまともに撮れたのはかなり後になってから。その頃にはもう囀ってなかったですよ確か。
2025.3.13 曇
ここ数日、林の雰囲気が春っぽく変わった気がします。鳴声のバリエーションが広がったのか種類が変化しているのか、どの声がどの鳥だか分からなくなっています。いつもの池、気づかずに不用意に近づいてアオサギを飛ばしてしまいました。そしていつもの林道で、ルリビタキの気配が薄くなった気がします。いるっちゃいるようなんですが。

カヤクグリ 2025.3.13撮影 高森町(860m)
自分のことながら、よく見つけたもんだ。

ミソサザイ 2025.3.13撮影 高森町(860m)
森の中にミソサザイの囀りが響き渡ります。この鳥も縄張りガッツリ系の行動パターンのようです。
カヤクグリもミソサザイも、棲んでる場所暗すぎな。ま天気もあるけーど。
2025.3.12 曇-雨

ちょっとした時間しかなかったので池と農耕地を1周。

カルガモ 2025.3.12撮影 高森町(660m)
今日は丘で採食のペア。ここ2羽より増えないってのは去年と同じペアが戻って来たのかなぁ。個体識別できるかなー。

カワラヒワ 2025.3.12撮影 高森町(700m)
果樹園のワイヤー

イカル 2025.3.12撮影 高森町(700m)
まだ囀りは聞いてないですけど地鳴きは聞こえていたイカル。久しぶりの撮影機会も、道路際での採食シーンだったので、クルマが1台通って終了。

アカゲラ 2025.3.12撮影 高森町(700m)
これまた久しぶりのアカゲラ。ん~コースを変えてみるっていいですね。いろんなところを回らないと。
2025.3.10 快晴
明日から雨予報で鳥撮りは期待できそうにないので今日楽しんでおきたいところ。

ニホンザル 2025.3.10撮影 高森町(840m)
なのに、ルリビタキやミヤマホオジロ狙いの場所に40頭ほどのニホンザルの群れ。野鳥は人だけじゃなく猿でも逃げますから、こういうときはこの周辺は諦めます。

アオサギ 2025.3.10撮影 高森町(660m)
去年の秋くらいからこの場所が気に入っていた若いアオサギ。池の氷が融けたのでさっそくやって来てた。カワセミも戻ってきてくれたら嬉しいな。
今日はカワガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、アオサギ、カルガモ。
2025.3.9 晴
朝から晴れ。標高840m付近の小川沿いの道でヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、カシラダカ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ミソサザイ。ミソサザイもカワガラスのように苔を集めていましたが、このポイントは晴れの日でも暗いので写真はちょっと難しい。
限られた時間をミヤマホオジロ見たさに林道に集中させているここ数日、なんか会える気配がない。

ミソサザイ 2025.3.9撮影 高森町(860m)
シルエットは小さいカワガラスみたいなミソサザイ。川岸で苔を集めているので巣作り中ですね。かわいい!
肉眼では「暗闇に動くものがある」くらい暗い場所だったので、そこそこ撮れててうれしい。かわいい。何度見てもかわいい。ちょこちょこ動いてたのでシャッタースピード1/1000で確実に止めようとも迷ったんですが、暗かったので1/400まで落として「止まれ!」って祈ってシャッター押しました。
2025.3.7

雨や曇り、寒い日の後の好天は野鳥の動きが活発になる印象。今日もミヤマホオジロ狙いで800m付近の林道へ出かけました。シジュウカラ、ヤマガラ、ヒガラ、コゲラ、ルリビタキ、エナガを目視。囀りはミソサザイ。林の中からヒガラが自分めがけて飛んできて、2m前の枝にしばらくとまってくれました。可愛いのと、せっかくの幸運だったので、カメラを構えず、肉眼でその時間を楽しみました。
今日は空の青さと南アルプスの白さのコントラストがハッキリした日でした。3月は13、14日あたりが夕方のアルプスと月の写真を撮りやすそうな日。今月は北岳の辺から昇るのかな、知らんけど。
水位が高めの天竜川は中洲にカラスが4羽ほど、たまにセキレイ。マガモとコガモ。岸でホオジロとモズ。

マガモ 2025.3.7撮影 高森町(400m)
久しぶりの天竜川。もうマガモとコガモしかいなくなっちゃったのかな。
2025.3.6
昨日は天気が悪かったので、今日やっといつもの衆のご機嫌を伺いに標高800m付近に出かけてみました。ホオジロ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、ルリビタキ。日が出てないので小鳥たちの活性が落ちている感じ。
町内のため池は氷が融けました。

ルリビタキ 2025.3.6撮影 高森町(840m)
撮れたのはルリビタキだけ。
2025.3.2番外編(宮古島)
たまたま松本空港から下地島空港に向かうツアーがあったのでフリープランで参加しました。松本空港から行けちゃうって、ホント楽でした。

午後4時過ぎに到着して、すぐレンタカーを借りて17ENDへ。飛行機が着陸する時間帯は観光客でにぎわいますが、そうじゃないとご覧の通り。駐車場から歩いて5分くらいで突端まで行けました。

イソヒヨドリ♀ 2025.3.2撮影 下地島
最初のご対面は17END先端、縁石の上でイソヒヨドリのメス。リュックからカメラ出す間、おとなしく待っててくれました。

クロサギ 2025.3.2撮影 下地島
駐車場へ戻ろうとすると、浜に初めて見るクロサギ。ところ変わればサギの色も変わる。

クロサギ 2025.3.2撮影 下地島
ごちそうにありついたはいいのですが、なかなか手こずってました。アイゴって魚らしいんですけど、ヒレが張り出しているせいか、丸飲みしか武器がない鷺は喉を通すのがかなり難しそうでした。

鳥は水辺にいるよねってことで、17ENDの近くにある通り池に行くと。

クロサギ 2025.3.2撮影 下地島
断崖にサギ二羽。クロサギと・・・、これ、ダイサギでもチュウサギでもコサギ?でもない感じ。もしかしたらクロサギの白とかいるのかな。指だけ黄色の足を見るとコサギ、でもコサギは脛がもっと黒くないか?脚で判断すると隣のクロサギも同じ脚。
なんか今まで見たコサギと雰囲気違うんだよな。
クロサギの白とか、ホント、最初の名前の付け方難しい。
ネットをざざっと見た感じ、やっぱりクロサギの白のようです。鳥撮り歴10ヶ月のビギナーなので、初見のクロサギ白を「クロサギ」と予想できたことがひそかにうれしい。

通り池を過ぎて岬の先端まで行ける木道があります。

イソヒヨドリ♂ 2025.3.2撮影 下地島
木道の手すりにとまって、観光地らしく人馴れしているイソヒヨドリ。この鳥は宮古島のどこ行っても必ずいます。

2日目は、まだ薄暗い朝6時から5時間かかて熱帯植物園を散策。写真は撮れなくても、動物の気配や影だけで相当楽しめました。

シロハラ 2025.3.3撮影 宮古島
まーシロハラ祭。そこらべったりシロハラ。草むらも木の枝も。おかげ様で過去一きれいなシロハラ写真撮れました。

ウグイス 2025.3.3撮影 宮古島
たぶんウグイス、ほぼ地鳴きだったけど、たまに聞こえる練習中の囀りは、これが正体だったんじゃないかなーって想像します。囀りの音が少し低く感じました。とにかく速い。まともに撮れない。
あ、そうそう、ウグイスって「うぐいす色」ってほど緑じゃないですよね。ほぼ灰色。

キンバトとか、ギンバトとかなんとか、ズグロミソゴイとかそういうレアな野鳥とは出会えませんでしたが、初めて聞く動物の声を聞きながら南国の森の中を彷徨う体験がとっても楽しい時間でした。5時間ほど歩いて最後に通りかかったのがこの池。「愛鳥家の皆さんへ」という注意書きがあるくらいなので、何かが現れるのかもしれませんが、このときは何もいなかったのでスルー。

ミヤコヒバァ 2025.3.3撮影 宮古島
白黒のオシャレな蛇に遭遇。帰って調べたらミヤコヒバァっていうらしいです。今すぐ絶滅ってわけじゃないけど、数を減らしている種類みたいです。

野鳥観察としては渋めの午前を過ごしたので、午後は場所を池間島に変えます。目的は池間湿地。ここも渋い!ぱっと見「なんもいねぇ」。オオバンが4,5羽。

ハシビロガモ 2025.3.3撮影 池間島
視力が弱いので肉眼でははっきりしなかったのですが、撮ったらハシビロガモが混ざっていました。初めて見ましたが、もうちょっと近くで見ないと「見た」って実感はありません。これで100mくらい距離あります。

ムラサキサギ 2025.3.3撮影 池間島
あ、なんかいる。アオサギかと思って撮ったらまた色違い。今度はムラサキサギっていうらしいです。色のバリエーション違いだけでもだいぶ面白い。

サシバ 2025.3.3撮影 池間島
あ、飛び出して飛んでったのは、たぶんサシバ。そうだ伊良部島へ行こう。・・・ということでサシバの渡りで有名な伊良部島へ行ってみたものの、簡単にサシバにも出会えず、サシバの形をした展望台で休憩して宿に戻りました。

サシバがあっち向いてる様子。だから後頭部と背中と左翼が見えてる感じ。ここの駐車場付近でギンバト2羽が茂みの中にいるのが見えたのですが、暗すぎてカメラ持ち出す気にもなれず。目視できれば嬉しさはゼロじゃないので、撮れなくても楽しいんです。とは言え釣果としては渋い、渋い1日。

残された時間はあと半日。鳥影が一番濃かった熱帯植物園の山林で朝日と共に探鳥開始。キンバト、ミソゴイ・・・。

ルリビタキ 2025.3.4撮影 宮古島
んんんルリビタキの若いオス?高原で過ごすルリビタキがこんな南国にもおるの?それに驚いた。

メジロ 2025.3.4撮影 宮古島
熱帯植物園最後の成果はメジロ・・・。うぐいす色の元になったのはこの鳥じゃないかって言われたりするメジロ。でもこれじゃ高森と一緒じゃ。残された時間は1時間。そうだサシバだ!サシバを撮ってない。空港に近づきながら下地島でサシバを探そう。

サシバ 2025.3.4撮影 下地島
サシバは下地島が探しやすい。今回のツアーは下地島空港発着だから助かる。

サシバ 2025.3.4撮影 下地島
1972年にサシバ猟が禁止されたというくらい、サシバが多く渡ってくる宮古島。最後に駆け足で帳尻合わせのサシバ写真が撮れて満足。

サシバ 2025.3.4撮影 下地島
2泊3日のフリーツアーで、宮古島ならではっていう鳥には出会えませんでした。それでも朝から夕方まで野鳥追って自由に過ごせて最高でした。
熱帯植物園で通りかかった池はレアな鳥がでる有名なところらしいのですが、ブラインドを用意して行くくらいの配慮が必要なところみたいです。道のすぐ脇なので、不用意に近づいて先客の邪魔をしてもあれなので、あまり近づきたくないです。
撮れなくてもそこら中鳥の気配があって楽しかった!また宮古島探鳥行きたい!
Tシャツ1枚で過ごしていた宮古島から松本空港に帰ってきたら吹雪で高速は交通規制がかかるっていうね。
2025.3.1
林縁、超獣害防止柵の際、新しい探鳥地でカケス、ルリビタキ、ガビチョウ。自宅でノスリ撮影、目視のみはヤマガラ、シジュウカラ、カワラヒワ、ヒヨドリ、アオジ、ホオジロ。シロハラの「プィプィ」が聞こえた。地鳴きの「チッ」単発は可能性が広くて嬉しくなります。ガビチョウは去年の5月以来。ルリビタキはメス限定だけど、けっこう個体数いる印象。

ガビチョウ 2025.3.1撮影 高森町(700m)
ピンボケだけど、記録。去年5月には出原で撮れた。ここは大島山。「大変!こんなところにまでガビチョウが!」てなるけど、ガビチョウに罪はないのよねー。にしてもエキゾチック。

ルリビタキ 2025.3.1撮影 高森町(700m)
メスはけっこう個体数いるなぁ。
2025.2.28

林道でヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ホオジロ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、カケスを目視。ミソサザイの囀りとカワガラスの声。自宅でカケス、ヒヨドリ、ノスリ、ヤマガラ、シジュウカラ、カワラヒワ、カラス、シロハラ。渓流でカワガラスがせっせと苔集め。

ノスリ 2025.2.28撮影 高森町(700m)
ノスリはやっぱり電柱が好き

ミヤマホオジロ 2025.2.28撮影 高森町(840m)
ホオジロが囀りだして、いろんな鳥の鳴き声にもバリエーションが増えた。
ミヤマホオジロを見たくて2日前と同じエリアをうろうろしていると、いた!けどまた遠い😆 同じエリアと言えば言えるけど、こないだの場所からは250mも離れてる。シジュウカラが主のヤマガラ、コゲラの混群に紛れている様子は前回と同じ。
2025.2.27
林道でヤマガラ、シジュウカラ、エナガ、ヒガラ、コゲラ、ルリビタキ、ホオジロ。ミヤマホオジロかもしれないと期待していた囀りはノーマルのホオジロだった様子。
鳥撮りを始めて10か月、初めて迎える初春です。少し暖かくなってきたここ数日、繁殖期を控えて活動が活発化してきている感じ。葉っぱが少なくて野鳥の活動が活発な今が、野鳥観察には一番いい時期かもしれない。

エナガ 2025.2.27撮影 高森町(840m)
エナガが何か綿っぽいものを幹から剥ぎ取って食べている様子。何だろう。巣の材料を集めているっていう線もあるけど、そもそも何だこの白いの。

ルリビタキ 2025.2.27撮影 高森町(840m)
常連のルリビタキ。ここは狭いエリアで2羽いるよう。縄張り意識が強い種類なので、気のせいか、片方がコソコソしている雰囲気。この季節には縄張りも確定して安定しているっていう話なのですが、縄張りが隣り合ってると、境界付近が気になるんですね、きっと。
暖かくなってきたので、そろそろもっと標高の高いところに行っちゃうんすかね。

ルリビタキ 2025.2.27撮影 高森町(840m)
ルリビタキやジョウビタキは、この時期、地面にいる虫を探しているっぽいです。だから、背丈の低い藪の枝にとまってキョロキョロして、虫をみつけると地面に飛び降りて捕食。
2025.2.26
最近カシラダカがよく出る水辺に出かけると、道路に4羽のカシラダカ。状況が厳しめだったので写真は撮らず。林道でも厳しい状況しかなかったので写真は撮らなかったけど、ルリビタキのメスと、ヤマガラ、シジュウカラを目視、さえずりはミソサザイとホオジロ。ちょっとシンプルなホオジロの囀りがミヤマホオジロじゃないかと期待したけど姿は確認できず。天竜川でカモ類、コガモ、マガモくらいか、遠すぎてカメラを出す気にもならず。家に帰っても何もいない。そんな日もあります。
2025.2.25
今日は新しい探鳥地に出かけてみました。そしたらヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、ミソサザイ、ミヤマホオジロ、ジョウビタキがいっぺんに押し寄せるという、楽園のような時間帯がありました。ただみんな動きが早い衆ばっかだもんで、それが日向に出たり日陰に入ったり、鳥撮りは困難を極めました。

ミヤマホオジロ 2025.2.25撮影 高森町(800m)
松島さんが探していたので存在を知りましたが、そんな鳥本当に高森町に来るのかと半信半疑でした。もう野鳥が春のさえずりを始める2月も終わりになって、ようやくそれらしき姿を記録に残すことが出来ました。立ち上がればもっと撮りやすかったと思うのですが、立ったら飛んじゃうと思ってこの角度と距離で我慢。フォーカス合わない💦
シジュウカラ、ヤマガラ、コゲラの混群と一緒にやってきた。藪から飛び出して地面を物色。
さっきから聞こえていたホオジロの囀りはこのミヤマホオジロ?

ルリビタキ 2025.2.25撮影 高森町(840m)
ずっと焦がれていたルリビタキも、年明けはけっこう見かける頻度があがってきました。気温や天候で出没エリアが変わりますが、まーまー本気で探せば1日に1回は会えます。この日も20m以内の距離に何度か現れてくれました。ジョウビタキと比べると鳴かない、静か。気が付くとそばにいたりして。やーそれにしてもオスに出会えない!やっぱり行動パターンがメスとちょっと違うんかな。

コゲラ 2025.2.25撮影 高森町(800m)
カラ類の混群おなじみのメンバー、コゲラも明るいところにとまってくれました。あ、そうそう、こないだ、庭にヒヨドリ、イカル、アカゲラの混群て言うのかなあれも、やってきて面白かったです。

ミソサザイ 2025.2.25撮影 高森町(800m)
コゲラが飛び去った後にやってきたのがミソサザイ。ねぐら近くで見つけると案外撮りやすいミソサザイも、こんな高い木の枝だととまっている時間は一瞬。よく撮れたもんだと、ファインダーに収めた自分とフォーカス合わせてくれたカメラを誉めてあげたいです。あっち向きだし影被ってるし、どっかに発表するような写真じゃないですけど、「ここでミソサザイに会えるのか!」的で嬉しい1枚。

ヒガラ 2025.2.25撮影 高森町(800m)
そんな珍しくないはずなのに、探鳥エリアがミスマッチなのかなかなか出会えないヒガラに遭遇。たぶんこれが3回目。前回は野鳥観察始めてすぐの夏くらいに電線の上でピンボケっていうの、たぶんヒガラでしょレベルの写真が撮れたとき。それとやっぱり野鳥観察始めてすぐの頃、暗い林道でガサガサに解像しないのを1枚撮ったとき、以来だったのでこれも嬉しかった。まぁまぁ撮れてる。
シジュウカラにしちゃ尾羽が短く感じたらやっぱり!って感じ。ただ、高い松の木で松ぼっくりの種を探しながらちょこちょこ飛び移るので、こりゃまともな写真は撮れんわって諦めていたところ、

ヒガラ 2025.2.25撮影 高森町(800m)
一羽が一瞬低いところに止まってくれました。

カシラダカ 2025.2.25撮影 高森町(660m)
昨日と同じポイントに行ってみる。群れじゃなかったのでホオジロかと思ったけど、念のためにカメラ向けたらカシラダカだった。周囲には本当に群れの気配はなかったんだけど。
2025.2.24
カシラダカの群れ10羽ほどと遭遇。

カシラダカ 2025.4.24撮影(660m)

カシラダカ 2025.4.24撮影(660m)
めずらしく藪から出て、氷が融けたところで水を飲んでました。種子を食べる系の野鳥は喉が渇きやすいという噂を聞いたことがあります。

カシラダカ 2025.4.24撮影(660m)
左がオスで右が・・・メス、かなぁ。冠羽はあるけどどことなく雰囲気が。

カワラヒワ 2025.4.24撮影(700m)
カワラヒワの鳴声が春っぽく、いろんなバリエーションが聞けるようになってきたと思います。

ヤマガラ 2025.4.24撮影 高森町(700m)
安定のヤマガラ。わりと近くに寄ってくれるので感謝してます。シジュウカラとヤマガラはよく一緒に行動しているので、けっこう異種間でコミュニケーションとれてるように見えちゃいます。

シジュウカラ 2025.4.24撮影 高森町(700m)
枝被りシジュウカラ。

ルリビタキ 2025.4.24撮影 高森町(720m)
ルリビタキのメス。うーん、やっぱりここは日常的な行動範囲内なんだ。でもココ一回だけオスいたのになー。
2025.2.22番外編
琵琶湖
用事で大阪に行くことになったので、途中で道草して探鳥。もうカメラ持ってないと不安なくらい出かけ得る先々でも野鳥のことばかり考えてます。

カワウ 2025.4.22撮影 琵琶湖
カワウ。冬の日本海の荒波ではなく琵琶湖。この日は吹雪でカワウもけっこう風で煽られてました。何羽か婚姻色になってます。

シロハラ 2025.4.22撮影 野田沼
シロハラ。高森町内で撮るのに苦労してるけど、あっさり撮れた。

オオワシ 2025.4.22撮影 琵琶湖山本山
琵琶湖といやぁ忘れられないのがオオワシ、20歳にもなろうという通称「山本山のおばぁちゃん」。野鳥センターで情報を集めるにも、今日は吹雪で視界が悪く、多くの人が見失っている状態だという。それでも雪がやんだ瞬間に地元のベテランのおじさんに教えてもらって撮ることができました。みんなけっこうな望遠レンズ。あとでgoogleマップで見てみたら、これで距離300mくらい。自分の機材じゃ頑張った方。
これは野田沼っていう場所から撮った1枚。野鳥センターに、近所に暮らしている方の迷惑にならないように、住宅街には入らないようにという注意書きがあったので、これ以上は近づかず遠慮。
ふらっと出かけた先で、吹雪の中、鳥を探すなんてときは、防塵防滴のMFTカメラにありがたみを感じましたね。普段InstaやYoutubeでフルサイズ機のレビューや作品を見て気持ちがソワソワしちゃいますが。

コガモ 2025.4.22撮影 野田沼
野田沼のコガモ。琵琶湖周辺は野鳥観察ポイントが多くてうらやましい。野鳥との距離感は都市公園ほど近くないけど、高森町ほど遠くない感じ。

ヒドリガモ 2025.4.22撮影 野田沼
野田沼のヒドリガモ。こーれも高森町には来てくれん、見つけてないだけかなー。飯島にはおったけど。
2025.2.21
テレコンが調子いい。

カシラダカ 2025.4.21撮影 高森町(700m)
カシラダカしか撮れずに意気消沈で帰宅。不意に夕方頃、自宅のモミジに遊びに来てくれて、なんとかフォーカス間に合った1枚。特に食べ物もなかったので、すぐ飛び去りましたけど。
さっき遠い絵しか撮れなかったので、なんか撮らせてくれたのかなって、そんなことないのにストーリー解釈しちゃうホモサピエンスの悪いクセ。

カシラダカ 2025.4.21撮影 高森町(840m)
1月に初めてカシラダカを認識できたときはイージーだなって思ったのに、その後どうも良いコンディションに出会えず、カシラダカはなかばあきらめ気味。最近探鳥コースに加えた場所で、それでも今日まで一度も見かけなかったのにカシラダカの群れに遭遇。でも遠い。絶望的に遠い。最近カシラダカの行動パターン変わったか?
今日はこれといった成果もなく、しょんぼり帰ろうとしたところだったので、遠いながらも癒された1枚。
2025.2.20
埃やマウントへの負荷が気になって、あまりレンズ交換したくないです。だからテレコンもつけっぱなし。

シジュウカラ 2025.2.20撮影 高森町(700m)
シジュウカラって、たまにこういう頭がペタッとした、オールバックのオッサンみたいなフォルムのがおる。

シジュウカラ 2025.2.20撮影 高森町(700m)
普通、っていうかよく見るのは、こういう、ふわっとした頭の形のシジュウカラ。

モズ 2025.2.20撮影 高森町(580m)(4
今日は久しぶりにモズが近くでよく撮れる日。さっきのモズとはまったく別の場所でメス。かわいい大きさのモズですが、小さな猛禽類と呼ばれるだけあって、何か小動物を捕食した形跡がくちばしのまわりについた血痕に見て取れます。

モズ 2025.2.20撮影 高森町(400m)
最近、モズにはかなり遠くから逃げられがちだったのですが、天竜川で久しぶりのモズのオスを撮影。松川町に出没するというアカモズでは、ない。

コガモ 2025.2.20撮影 高森町(400m)
探鳥に訪れる頻度が落ちている天竜川。理由は野鳥が”遠すぎる”から。これも100mくらいあるのをレンズが頑張ってここまで解像してくれたもの。とは言え羽毛の質感云々を言えるレベルではないです。たぶんコガモ。上野で買ってきたテレコンが威力を発揮しています。

ルリビタキ 2025.2.20撮影 高森町(840m)
都市公園から高森町に帰ってきて、枝被りつつも最初に出迎えてくれたのはルリビタキのメス。お出迎えありがとうございます。このくらいで撮らせてもらえたら嬉しいです。できれば今度知り合いのオスも紹介してください。
2025.2.18番外編(不忍池)
東京上野
上野の国立科学博物館で開催されている「鳥展」を見に行ってきました。もちろんカメラ持って。超望遠レンズ付けても三脚なしで散歩がてらシャッター切れるマイクロフォーサーズの恩恵を実感。近くにヨドバシカメラがあったのでふらっと入ったら1.4倍のテレコンの在庫があったので、上野まで来た勢いで買ってしまいました。

キンクロハジロ 2025.2.18撮影 不忍池
キンクロハジロがこの距離で撮れるなんて。10mくらい。高森町のカモは、50m、いや100mくらいで逃げちゃいます、たぶん。

キンクロハジロ 2025.2.18撮影 不忍池
キンクロハジロ。この距離で人がいる方向に泳いでくる。後頭部の飾り羽が風で寝グセみたい。

オナガガモ 2025.2.18撮影 不忍池
安曇野で対面済みのオナガガモ、人がすぐ横を通る池の岸でお休み。なんかホント、天竜川でカモの写真撮るなんて何の修行だろう。あくまで野鳥”観察”だって言い聞かせないと心が折れそうになる。

ユリカモメ 2025.2.18撮影 不忍池
ユリカモメっていうらしい。このサイズの鳥がトリミング無しで撮れるって・・・。都市公園恐るべし。

アオサギ 2025.2.18撮影 不忍池
町内だと最短で50mくらいかな、のアオサギも、トリミングなしどころか脚が入らないっていう。近すぎて超望遠じゃ撮れないので、あえて離れて撮る。

アオサギ 2025.2.18撮影 不忍池
トリミングなしで顔アップ。
田舎もんなんで、うれしくてついつい寄ってアップばっかり撮っちゃう。

ツグミ 2025.2.18撮影 不忍池
町内で案外撮れないでいるツグミ。出会えてもたぶんこんなに寄れないと思われる。

ツグミ 2025.2.18撮影 不忍池
トリミングなしツグミ。画面中央にフォーカスエリア設定してると尾羽が切れるっていう、町内ではできない経験。

コサギ 2025.2.18撮影 不忍池
そりゃそうでしょうよ、コサギだって逃げません。カメラ縦にしてやっと全身入る。トリミングする余地なし。コサギの特徴、黒い脚と黄色い指がよく確認できます。

ムクドリ 2025.2.18撮影 不忍池
町内でもいつでも撮れそうと思って油断していまだ撮れていなかったムクドリ。近すぎて離れるのに苦労します。自分が他の歩行者にぶつからないようにするために。
2025.2.17番外編(安曇野編)
目的地は上野、鳥展が目的。せっかく東京に行くなら都市公園で野鳥を撮ってみたいので、当然のように超望遠を持っていく。そうなると、出かけたついでに安曇野にも行きたい。白鳥が北に帰る前に。そんなわけで安曇野経由で佐久平駅、新幹線で上野駅というルートを選択。

コハクチョウ 2025.2.17撮影 安曇野 犀川白鳥観察館
コハクチョウはこの日の午後から北帰が始まったようで、ギリギリでした。う~ん、逃げない。

コハクチョウ 2025.2.17撮影 安曇野 犀川白鳥観察館
いつも、ただの山ん中で野鳥を撮ってるので、こういう場所でのマナー、ローカルルールが分からないので、白鳥や他の人に迷惑にないよう恐る恐る撮影。

コハクチョウ 2025.2.17撮影 安曇野 犀川白鳥観察館
撮れた撮れた。今日は道草なのでこれだけ撮れれば満足。場所の様子も分かったので、来季はしっかり計画たてて撮ろう。

オナガガモ 2025.2.17撮影 安曇野 犀川白鳥観察館
観察館の駐車場の向こう側に、元々は犀川の一部だったんだろう三日月湖的な池があって、そこがカモ撮影の楽園。このカモたちの距離感が分からない。飛ばれると嫌なので、遠めから遠慮がちに撮影。オナガガモ、きれいだなー。いや~楽園。

オナガガモ 2025.2.17撮影 安曇野 御宝田遊水地
観察館も楽園だったけど、カモに限定すると、同じ犀川沿いの御宝田遊水地がもっと楽園。距離とか逃げるとか飛ぶとかそんな概念のないエリア。誰もいなかったので、ここのルールを聞けず、やっぱり恐る恐る撮影。

オナガガモ 2025.2.17撮影 安曇野 御宝田遊水地
高森じゃまず撮れないショット。こんだけ近いと超望遠じゃなくて広角がもっと面白い写真撮れるかも。

カワウ 2025.2.17撮影 安曇野 御宝田遊水地
高森じゃ、眼球が緑ってことが分かれば上出来のカワウ。光彩まで撮れるなんてね。
ここに立ち寄れる時間は10分間だけだったので、鳥の近さに圧倒されているうちに制限時間。ほとんどのカモ達はもうじき北に出かける頃だと思われるので、ここは来年もっと落ち着いて挑戦しよう。
2025.2.14
カワガラスの巣作り継続中

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
巣の材料となる苔を咥えて帰ってきました。

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
「あの隙間にこう、スッと・・・」

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
水に強いカワガラスとは言え、一応、流れの隙間を狙っているみたい。

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
でも最後はエイヤッ!って感じ。体半分は水に当たってる。もうちょっと左だったかぁ。

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
結果オーライ。
出かけるときは

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
こうやって羽ばたかずにヌルっと飛び降りて

カワガラス 2025.2.14撮影 高森町(720m)
この辺から羽ばたいて飛んでく感じ。
2025.2.12
野鳥観察は渋い1日。ここへ来るとカワガラスは撮らせてくれるのでありがたく。

カワガラス 2025.2.12撮影 高森町(720m)
雪が融けて、再び巣作りの苔集め開始の様子。
2025.2.10番外編(諏訪湖)
諏訪湖に逃げないカモ類がいるって体験が忘れられずに、鳥撮る目的だけで行ってきました。諏訪湖の岸に望遠レンズ持った人が2人。初めて自分以外で超望遠で野鳥とっているおっさん達に遭遇しました。

ミコアイサ 2025.2.10撮影 諏訪湖
釜口水門でミコアイサ。吉瀬ダムで400mくらいの距離、肉眼では見えないくらいのところで一度みたことのあるけどこの距離は初めて。

キンクロハジロ 2025.2.10撮影 諏訪湖
諏訪湖の岸ちかくにカモがいっぱいおるのですが、時間帯がまずかったようで、ほとんどが昼寝中。

ホオジロガモ 2025.2.10撮影 諏訪湖
手前で目を開いて休んでいるのがホシハジロで、奥の白黒のがホオジロガモ。ホシハジロはたまに天竜川に最多で4羽くらいいますがほとんど見えません。ホオジロガモに至っては一度も見たことがないです。

カンムリカイツブリ 2025.2.10撮影 諏訪湖
始めてみました。ほとんどが寝てましたが、首を持ち上げた1羽の顔が撮れてラッキーでした。

カワウ 2025.2.10撮影 諏訪湖
頭が真っ白で初めてみた野鳥かと思ったらカワウの婚姻色なんですって。始高森町内ではまだ婚姻色を見たことがありません。

カワウ 2025.2.10撮影 諏訪湖
虹彩まで撮れてる。カワウがこんなに近づかせてくれるなんて。

オオバン 2025.2.10撮影 諏訪湖
オオバンも町内の池では警戒心強めな部類。ここ諏訪湖では人間を無視して餌を探してます。カモ類とは違う足の形がよくわかります。

ヒドリガモ 2025.2.10撮影 諏訪湖
松島さんの話では、町内でもみられるはずのカモですが、私は一度も確認できていません。どーせ町内でみかけても近づかせてくれないと思います。諏訪湖沿岸の芝生で餌をとるのに一生懸命で、人間の存在ガン無視です。

コハクチョウ 2025.2.10撮影 諏訪湖
今年は安曇野までしか南下してこないという噂を聞いていたコハクチョウが諏訪湖にも2羽いました。望遠レンズを持った人が私以外に2人、30mと35mくらい離れたところでカメラを構えていましたが、スマホ持ったおじさんが10mくらいまで近づいていて、「野鳥にはあまり近づき過ぎないように」というのは野鳥撮影趣味の人達の間だけでのマナーで、野鳥撮影しない人たちにしてみればコハクチョウもただの鳥だし、近づいちゃいけない法律もないし、ということを感じたシーンでした。私は遠慮ぎみに50mくらいのところから撮影。
2025.2.9
昨夜から今朝にかけて雪、そして晴れ。今日も期待できる日。

ジョウビタキ 2025.2.9撮影 高森町(720m)
雪の次の日が晴れだと、前日の地面が雪で覆われてしまうので、藪の中の地面で虫探しをする野鳥達が、雪が早くとける舗装道路付近に出てきやすいです。昨日と同じ場所にジョウビタキ。

ルリビタキ 2025.2.9撮影 高森町(720m)
ルリビタキも道路際でちょろちょろ。あと小川の周辺で雪が融けた石の上にもいました。
2025.2.8
雪の日明けで曇天が続いて幸運。今日も除雪された道をたどる。

ルリビタキ 2025.2.8撮影 高森町(740m)
日当たりが良く、午前中のうちに雪が融けるような道に、普段はみかけないルリビタキ。

ジョウビタキ 2025.2.8撮影 高森町(740m)
ルリビタキと同じ通り、除雪跡にジョウビタキも登場。こういう場面はジョウビタキもルリビタキも雌ばかり。

カヤクグリ 2025.2.8撮影 高森町(900m)
ルリビタキと同じ通りにカヤクグリも現れました。そして標高900m付近でも除雪跡にカヤクグリ。しつこく長時間にわたって、露出した地面をつついていました。
2025.2.7
昨夜は雪で今朝が晴れ。除雪された道で探鳥。

カシラダカ 2025.2.7撮影 高森町(660m)
いつもの探鳥コースに向かう途中の道路にカシラダカ。除雪後の道路はホント、ワクワクします。

ルリビタキ 2025.2.7撮影 高森町(720m)
過去2回チラ見して以降、しつこく通い続けている場所で、やっとオスのルリビタキが撮れました。「こんなところにいるはずなんだよな~。」って横みたら本当にいて、慌ててカメラの設定が間に合わず。

ルリビタキ 2025.2.7撮影 高森町(740m)
春以降、あまり成果がなくて足が遠ざかっていた道を久しぶりに訪ねたらルリビタキ。ここにいつもいるのかな。

ジョウビタキ 2025.2.7撮影 高森町(700m)
いつもウチの車庫をねぐらにしているジョウビタキ。最近は5時20分頃に帰ってくることが分かっていたので待ち伏せて撮らせてもらいました。朝は6時30分頃になるとでかけていきます。オスはよく建物の軒下をねぐらにすることがあるようです。メスはそんなことないんですって。確かにメスは山に行かないと出会えない。
2025.2.6
寒波到来。

ルリビタキ 2025.2.6撮影 高森町(700m)
今日もカワガラスの観察地、渓流の岸でルリビタキ。寒波の間は行動パターンが変わるみたい。

アオジ 2025.2.6撮影 高森町(700m)
ちょっと強めの舌打ちみたいな単発の地鳴き、正体はアオジでした。除雪後の道路で餌探し。
2025.2.5
寒波到来。

ジョウビタキ 2025.2.5撮影 高森町(700m)
寒くて球体に近づいているジョウビタキ。

ルリビタキ 2025.2.5撮影 高森町(700m)
なかなか出会えなかったルリビタキ、最近は登場頻度が高い。撮れ出すと、カラ類より落ち着いているので撮りやすい。
2025.2.2

ヤマガラ 2025.2.2撮影 高森町(700m)
2025.2.1

ベニマシコ 2025.2.1撮影 高森町(720m)
2025.1.31
今朝は林道でジョウビタキ、探鳥地開拓中に走ってた道路沿いで出会い頭のハギマシコ。

ジョウビタキ 2025.3.31撮影 高森町(720m)
ベニマシコやルリビタキが現れる場所にジョウビタキも。縄張り被ってると思う。

ハギマシコ 2025.3.31撮影 高森町(760m)
野鳥観察ポイントを探して町内を移動中、道路沿いの雪が融けた場所で不意にハギマシコ。とりあえずシャッタースピード1/400で収めといて、これからじっくり撮ろうというところで、クルマや散歩の人で、飛び去ってしまいました。残念だけど野鳥あるある。
(番外編)諏訪湖
夕方、諏訪に用事があったので、一応カメラを持っていきました。本来の用事より、どこに出かけたらどんな鳥がいるのかが気になっちゃって。湖畔の駐車場に車を停めて野鳥を撮れたのはたった15分。

ヒドリガモ 2025.1.31撮影 諏訪湖
駐車場の土手にカモ。一度だけみたことがある、これはヒドリガモ。15羽ほどの群れで一心不乱に芝生の何かを食べている様子。人や車がガン無視。また遊歩道を歩いている人達もカモの存在は当たり前のようでガン無視。
へ~なにコレ撮り放題!

オオバン 2025.1.31撮影 諏訪湖
高森町内でみかけるカモ的な(クイナ科だけど)野鳥の中で、一番距離をとられるオオバンが人影で逃げないって・・・。ありがとう諏訪湖、ありがとうオオバン。
初めて見たときは、こんな珍しい顔した鳥を発見できてラッキー!って思ったけど、けっこうどこにでもいるなオオバン。

マガモ 2025.1.31撮影 諏訪湖
オオバンと張り合うくらい人キライなマガモも諏訪湖では話が別。超望遠の画角からはみ出すくらい近くに来てくれます。これはむしろ寄ってきている感じ。そっか餌付けか~、餌付けね~。でもありがたい。
たった15分間で、これまで撮ったことのないような体験ができました。鳥目的でもう一回来たい。
2025.1.30
寒波到来中

カワラヒワ 2025.1.30撮影 高森町(700m)

アオジ 2025.1.30撮影 高森町(700m)
いつもはホオジロしかいないような場所で、ここ数日、大き目の舌打ちしたような「チッ」って単発の地鳴きが聞こえていたので、何か未知の野鳥がいると思っていましたが、正体はアオジでした。
2025.1.28
今朝は陸が静かだったので、小川でカワガラスに相手してもらいました。

カワガラス 2025.1.28撮影 高森町(660m)
苔集めを始めていました。まだ1月ですが、もう巣作りの時期なんですね。
2025.1.26(番外編)吉瀬ダム
今日はビリンジャーの作業を終えたあと、松島さんと吉瀬ダムへ向かいました。

キンクロハジロ 2025.1.26撮影 吉瀬ダム
吉瀬ダムは現在改修工事中で、1年くらいは水を貯めていないそうです。なのでほぼ普通の天竜川。水鳥達はダムから400m上流の辺にいたので識別がやっと。キンクロハジロの群れにホシハジロ、ミコアイサが混ざっている群れでした。ミコアイサは初対面。対面してないけど。
2025.1.24

ジョウビタキ 2025.1.24撮影 高森町(700m)
あ、ジョウビタキって昆虫食だけじゃないんだ。

シロハラ 2025.1.24撮影 高森町(680m)
シロハラ撮りたいと思って、放置されている柿の木がありそうな場所に行ったら当り。もう柿の実は落ちちゃってたけどシロハラには会えました。
(番外編)飯島町
飯島に用事があったので当然カメラ携帯。農業用ため池。

キンクロハジロ 2025.1.24撮影 飯島町
キンクロハジロとホシハジロ。遠い。人の気配を感じると対岸側にスススーって移動しちゃいます。
2025.1.21

カワガラス 2025.1.21撮影 高森町(660m)
つがいで生活しているっぽいけど、行動のタイミングとか距離感は近すぎない、いつも一緒って感じではない様子。
2025.1.20

ジョウビタキ 2025.1.20撮影 高森町(700m)

ヤマガラ 2025.1.20撮影 高森町(700m)

シジュウカラ 2025.1.20撮影 高森町(700m)
気まぐれで飛翔撮影に挑戦してみた。1/3200で止まらないのね。なるほど、これは設定から光の環境からちゃんと計画立てて訓練しないと撮れないわ。でもまーしばらく止まりものでいいな。飛び立つのを待つのがエラい。
(番外編)飯島町
仕事で通りかかった飯島の野池。

アオサギ 2025.1.20撮影 飯島町
アオサギ、ヒドリガモ、カルガモ、コガモ?

オカヨシガモ 2025.1.20撮影 飯島町
初見のオカヨシガモ。

キジバト 2025.1.20撮影 飯島町
なんの水鳥だろうと思って撮ってみたらキジバトだった。こんなどっぷり水に浸かってるとこ初めて見た。
2025.1.19

カワガラス 2025.1.19撮影 高森町(660m)
もう少し解像感高めのカワガラスが撮りたくて川に通ってます。警戒度が日によって違うので、しっかり距離をとってるつもりでも飛んじゃうときがあります。
猿の群れが近づいても飛ぶので、飛ばすこと自体が悪じゃないんですけど。
2025.1.18

キセキレイ 2025.1.18撮影 高森町(800m)
ハクセキレイ、セグロセキレイがそこそこの解像感で撮れてるんですけど、キセキレイだけが今一つ。これも羽毛の質感は全然。
2025.1.17

ニホンザル 2025.1.17撮影 高森町(660m)
今日はおサルだけ。この季節になっても果樹園はターゲットなのか熟々のリンゴ食べてる。
2025.1.16

ニホンリス 2025.1.16撮影 高森町(660m)
ベニマシコ待ちで遭遇。たま~の登場なので、けっこう嬉しい。

ベニマシコ 2025.1.16撮影 高森町(660m)
茶色系じゃない野鳥って会うと特別な嬉しさがあります。オスが2羽で行動している様子。メスが近くにいるかどうかは確認できず。

ジョウビタキ 2025.1.16撮影 高森町(680m)
1mくらいの杭の上とか大好きなジョビ。
2025.1.14

ベニマシコ 2025.1.14撮影 高森町(660m)
地味な茶色の方が安心して暮らせそうなのに赤色って。

ジョウビタキ 2025.1.14撮影 高森町(660m)
オスは人んちの軒先にねぐらを構えたりするので住宅地でみ見かけますが、メスが民家をねぐらにするということはないそうで、こうして山や公園、林道にでかけないと会うことができません。
2025.1.13

ニホンリス 2025.1.13撮影 高森町(660m)
ベニマシコ待ちのニホンリス。カラ類やヒタキ類の野鳥と比べると、尻尾も含めて、相当大きいものが動いてるって印象で、いれば存在には気づきやすいです。

ジョウビタキ 2025.1.13撮影 高森町(660m)
ここら一帯はこのジョウビタキの縄張りっぽい。ということはルリビタキはこのエリアにはいないってことなのかー?
2025.1.12

ベニマシコ 2025.1.12撮影 高森町(660m)
松島さんに教えていただいたカシラダカ待ちのポイントにベニマシコ。

カシラダカ 2025.1.12撮影 高森町(680m)
カシラダカの群れに遭遇、そのうちの1羽。これでも目立つ場所にとまってくれてる方。

カシラダカ 2025.1.12撮影 高森町(680m)
その他大勢は地面で採食。これが見えない。分かります?
2025.1.11

ルリビタキ 2025.1.11撮影 高森町(660m)
存在に気づいて1枚だけシャッター切れた。初ルリビタキ♀だ!メスの尾羽だけ青いっていうのも綺麗だ。間違いない、ここはルリビタキいる。ピント合ってないけど自分史上貴重な1枚。
2025.1.10

ヤマガラ 2025.1.10撮影 高森町(700m)

ヒヨドリ 2025.1.10撮影 高森町(700m)
どこにでもいて、あまり人気のない、むしろ農家から嫌われているヒヨドリ。それはそれとして野生動物としてはけっこうカッコいいと感じるので、もっといい写真撮ってみたいって思います。

アオジ 2025.1.10撮影 高森町(700m)
ヒヨドリが去った後にエナガが来て熟しをつついとる。

アオジ 2025.1.10撮影 高森町(700m)
もっといろんなところで見かけてもいいと思うけど、ここでしか見ない。

カワラヒワ 2025.1.10撮影 高森町(700m)
今後カワラヒワをこのサイズで撮ることはない気がするくらい、ちゃんと撮れた。

アトリ 2025.1.10撮影 高森町(700m)
ボケボケのカシラダカ? んにゃ、胸の模様とか考慮すると、アトリ。
2025.1.9

シロハラ 2025.1.9撮影 高森町(700m)
声はすれど姿が見えずだったシロハラをやっと撮れました。いや、撮ってみたらシロハラだったって感じ。プィプィプィプィ!って独特の鳴声です。
鮮明じゃないですけど、またどこかで撮れる機会ありそう。あるはず。
2025.1.8

シジュウカラ 2025.1.8撮影 高森町(700m)
雪の日のシジュウカラ。

ヤマガラ 2025.1.8撮影 高森町(700m)
雪の日のヤマガラ。
2025.1.5

ミソサザイ 2025.1.5撮影 高森町(960m)
初対面のミソサザイ。小さい!
2025.1.3

ヤマガラ 2025.1.3撮影 高森町(700m)
朝と夕方の光線がいいんじゃないかって思い始めて。
2025.1.1

ヤマガラ 2025.1.1撮影 高森町(700m)
ウチの庭が縄張りらしいジョビオと初日の出を拝む。

エナガ 2025.1.1撮影 高森町(700m)
元旦からエナガも遊びに来てくれた。

ベニマシコ 2025.1.1撮影 高森町(660m)
横顔に朝日を受けて、すすきの穂も光ってカッコよかったっす。
その者赤き衣をまといて金色の野に降り立つべし。
2024.12.31
2024年最後の日もしっかり探鳥。会社が休みっていーよねー> <

イソシギ 2024.12.31撮影 高森町(400m)
もっと出会える想定で初対面。

イカルチドリ 2024.12.31撮影 高森町(400m)
この日はシギチのラッキーデイ。

タヒバリ 2024.12.31撮影 高森町(400m)
天竜川の中州にタヒバリ?

エナガ 2024.12.31撮影 高森町(700m)
最近、ちょっと大きめに撮れるようになったエナガ。

メジロ 2024.12.31撮影 高森町(700m)
野鳥はアリングまでしっかり撮れると相当嬉しい。
2024.12.30

正月休みに入り、冬鳥ウォッチング満喫中で今日は大漁大漁。

ジョウビタキ 2024.12.30撮影 高森町(700m)
丸いっていうより、ぽてっとしたジョビオ。50㎝から1m程度の高さにいるところを見かけがち。

ヒヨドリ 2024.12.30撮影 高森町(700m)
南アルプス方向を眺めるシルエットがかっこいい。何の木だか分からないけど、芽吹きの季節が近い。

メジロ 2024.12.30撮影 高森町(700m)
朝日に当たるメジロ。

ベニマシコ 2024.12.30撮影 高森町(660m)
朝のお食事中。

ベニマシコ 2024.12.30撮影 高森町(660m)
ベニマシコのメス。これもやさしい色してるなー。

ルリビタキ 2024.12.30撮影 高森町(660m)
超絶暗い場面で動き回る鳥影を相手にやっとこさシャッター切れた1枚。これたぶんルリビタキのオス。

モズ 2024.12.30撮影 高森町(400m)
こちらの存在には完全に気づいてる。けど飛ばずにいてくれてありがとう。

ジョウビタキ 2024.12.30撮影 高森町(400m)
このジョウビタキもこちらの存在には完全に気づいてる。けど飛ばずにいてくれてありがとう。このフォルム、ぬいぐるみか!可愛すぎる。

カシラダカ 2024.12.30撮影 高森町(660m)
カシラダカ。見えないでしょ?目じゃなく耳で探す。「チッ」「チッ」っていう単発の舌打ちみたいな地鳴きを聞き逃すな。

エナガ 2024.12.30撮影 高森町(700m)
ジルル、ジルルって賑やかな声が聞こえてきたらエナガ軍団。ここんとこ連日会えてる。
2024.12.29

寒い日が続きます。今日は天竜川方面へ。

スズメ 2024.12.29撮影 高森町(400m)
家の近所には少なくて、畑にいても距離とられるし、そうじゃなきゃ高い電線の上で逆光とか多いスズメ、やっと目線の高さで撮れた。

チョウゲンボウ 2024.12.29撮影 高森町(400m)
天竜川の堤防、遠くから石に見えたのがチョウゲンボウでした。野芝の土手の上にちょこんと、休んでいるのか、潜んでいるつもりなのか。猛禽類で一番かわいらしいんじゃないですか。

カワラヒワ 2024.12.29撮影 高森町(700m)
道路際の土手や道路に降りて種子を拾ってる。カワラヒワはまーまー群れ。たまに単独のもいるけど稀。カシラダカを探してるのですが、カメラ向けるとまーまーカワラヒワ。

キセキレイ 2024.12.29撮影 高森町(700m)
キセキレイと言えば道路際。人の生活に近いところ。何度も出会ってるけど、どうしてもちゃんと撮れない。
2024.12.28

ダイサギ 2024.12.28撮影 高森町(400m)
珍しくもないし、魚関係者には嫌われてるし、警戒心強いし。でも単に野鳥としては相当好き。

カワガラス 2024.12.28撮影 高森町(400m)
画面中央にいます。珍しくはないけど、その存在を知る人がほぼいないカワガラス。この寒い日に天竜川の流れの中で餌探し。

カワガラス 2024.12.28撮影 高森町(400m)
羽毛の撥水がすごい。
2024.12.27

ハイタカ 2024.12.27撮影 高森町(400m)
小雨が降る中、堤防沿いの木にとまったカワラヒワでも撮ろうかというところで、カワラヒワの群れを蹴散らして登場したのがハイタカ。思ったより小さい、ハトくらい。
2024.12.26

イカルチドリ 2024.12.26撮影 高森町(400m)
天竜川の中州、カモたちが休んでいる岸で。
2024.12.25

昨日の仙丈ケ岳

カワアイサ 2024.12.25撮影 高森町(400m)
天竜川の中州の流れが緩やかなところには多数のカモたち。

ホオジロ 2024.12.25撮影 高森町(400m)
カシラダカと似てるホオジロのメス。
2024.12.23

天竜川から仙丈ケ岳
天竜川から前山が遮るので南アルプスほとんど見えない。

カワアイサ 2024.12.23撮影 高森町(400m)
近くで見てみたいなー。

ヒガラ 2024.12.23撮影 高森町(840m)
ヒガラもゆっくり撮らせてくれないグループ。
2024.12.22

天竜川から仙丈ケ岳
高森町の下段からは仙丈ケ岳が映える。

ダイサギ 2024.12.22撮影 高森町(400m)
サギのたまり場でリニアの橋脚工事が始まったので、支流に避難していたダイサギを通りすがりに撮れた。さすがにこの距離じゃすぐ飛ばれたけど、道から撮るのは罪ないよねぇ。

セグロセキレイ 2024.12.22撮影 高森町(400m)
天竜川はセグロセキレイが主で、キセキレイ、ハクセキレイはほぼ見ない。

カワガラス 2024.12.22撮影 高森町(400m)
水かきもないのに水中で採食するカワガラス。天竜川の激流にも負けない、っていうか負けて流されてるけどくじけない。

カワアイサ 2024.12.22撮影 高森町(400m)
ワカサギを食っちまうて諏訪湖では嫌われているカワアイサのつがい。撮るだけなら色形が面白くていい、なんだろ、こう、ちょっとヤンキー的な。
2024.12.19

上段道路から北岳

クロジ 2024.12.19撮影 高森町(900m)
藪の中にクロジ。
2024.12.17

上段道路から塩見岳

セキレイ 2024.12.17撮影 高森町(700m)
ハクセキレイがこんなにちゃんと撮れたの初めて。
2024.12.16

上段道路から塩見岳

カワウ 2024.12.16撮影 高森町(400m)

コガモ 2024.12.16撮影 高森町(540m)
眠そう。
2024.12.12

上段道路から北岳

ノスリ 2024.12.12撮影 高森町(700m)
ずんぐりしたノスリだなぁ。寒いのか

ハシボソガラス 2024.12.12撮影 高森町(660m)
なんかカラスに緊張感が漂ってると思ったら

オオタカ 2024.12.12撮影 高森町(660m)
いた、オオタカ。カラスって、猛禽類に対して逃げるだけじゃなくて見張りしたり追い払ったり、印象がいい。
2024.12.10

上段道路から塩見岳

ダイサギ 2024.12.10撮影 高森町(400m)
競い合ってる感。知らんけど。

やっぱり塩見が好き 2024.12.10撮影

カルガモ 2024.12.10撮影 松川町
2024.12.9

上段道路から仙丈ケ岳

ジョウビタキ 2024.12.9撮影 高森町(700m)
ジョウビタキは特に丸い。
2024.12.8

上段道路から前山
アルプスは見えず

ホシハジロ 2024.12.8撮影 高森町(580m)
奥はオオバン。