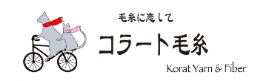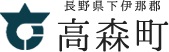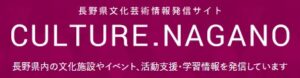2021年9月に役場の前で撮影した1枚。若手の新人議員が4名誕生したということをお伝えしました。あれから4年が経ちました。7月20日には次期町会議員を決める選挙があります。
今回は本島議員に新人議員として奮闘した4年間の様子をお聞きしました。

議員さんのお仕事といえば議会。一般質問で町の事業や考え方を質すっていうイメージがありますけど。
一般質問はこの4年間で8回やりました。主題は子育てに関することが多かったです。子ども達に誇れるまちづくりが大切だっていう思いがありますから。
・人口自然減少抑制に関する施策
・高森町版ネウボラとは
・学校給食の食育推進状況は
・こども基本法の学びはどうする
・今後のマスク着用の考え方は
・学校防災体制を整備するには
・教科担任制の児童生徒の反応は
・包括的性教育への切り替えは
・TOCO-TONの今後の取り組みについて
定例議会や全員協議会、委員活動の他に取り組んだことはありますか?
議会基本条例の制定に向けては頑張りましたよ。
議員のやるべきことを明確にして、町民にも説明できるようにしたいという思いがあって、そのために議会基本条例を作らなきゃってことで、有志の議員と協力して活動していました。
すんなり制定できたんですか?
いいえ。そもそも高森町議会には「高森町まちづくり基本条例」というものはあって、この中に「議会の責務・議員の責務」の記述があるから「新たな条例を作る必要はない」と考える人達もいて、なかなか難しかったんです。
でも未来の高森町のためにも、今年の7月までにはどうしても制定にこぎつけたくて、仲間の有志議員と協力して活動を続けました。条例制定に向けて「議会・議員のやるべき事を町民にも明らかにするべき」と目的を明らかにし、毎週の会議を重ねることで、去年の9月定例会で「高森町議会基本条例」を制定することができました。
他には?
あとは議会町民懇談会ですかね。
議会と町民のコミュニケーションの場として、懇談会が必要だとアピールしていたんですが、コロナの影響で実現できなかったんです。令和5年5月に新型コロナが「5類感染症」になったのをきっかけに、「町民の皆さんに会いに行けない理由が無くなりました!懇談会やりましょう!」と有志議員と協力して、めげずに訴え続けた結果、議会町民懇談会を開催することができたんです。
議会の外では何かありますか?
あったかてらすでワークショップをやっています。小さなお子さんをお持ちのママさんやご家族の皆さんのお困りごとを、雑談やワークショップを通じて気軽な気持ちで話してもらっています。子育て世代のニーズ把握にとても大切な場になっています。
あと、いろいろな施設や団体への訪問、聞き取り調査をやりましたね。いろんな地域課題に合わせて、それぞれの種関係施設を訪ねて聞き取り調査をしたり、依頼者の方と一緒に施設を訪ねるっていうこともやっています。お気軽に声かけていただければ。
この4年間で見えてきた課題とか、ありますか?
議会が町民のみなさんの意見を聞く機会が少ないって感じました。町民懇談会は開催できたんですけど、もっといろんな団体・組織・グループなどと行える方法、例えば定期開催やオンライン会議とか、まだまだ検討が必要だと感じます。
あとは議会としての情報発が弱いこと。情報の質、量、タイミングをしっかり考えて、SNSや動画を上手に使うことも大事だと思います。
あと、議員報酬を増やしたいです。なり手不足の決定的な問題が議員報酬だと思っていて、報酬について早急に検討に入ることが必要だと思います。
町づくりに関して今、本島さんが興味を持っていることは?
食料問題
自給率、食育、防災、自己完結型フードシステム、コミュニケーション、成功体験、自由研究。例えば植物の種ってすごいんです。小さな鉢植えからでいいので、1種類から「買う」以外の選択で心と生活が豊かになる、そんな取り組みを町民の皆さんと一緒にしていきたいです。
子どもの権利ファースト
子ども達の今と未来を守るために、時の大人の都合で脅かされてきた私たち大人が、同じことを繰り返さない。子どもの権利条約・子ども基本法心とからだの成長段階を、正しく心穏やかに知ることが必要だと思います。子どもの可能性は無限大!
相互扶助
お互いに手を取り合って、支えって守りあって結び合う相互扶助。1人では無理でもいろんな人と協力することで実現する豊かさに気づける地域がいいなって思います。それにはコミュニケーションが大事で、双方の気持ちや考え方が相手に伝わって、理解が深まって、信頼関係を気づいていく事によって、精神的な充足感や安心感から様々な豊かさが得られると思います。
最後に、まもなく1期目4年間が終わりますが。
今の世代だからこそ出来ること、やりたい事がまだあるので、絶対に次の議会にも立ちたいです!
次期には議会内で挑戦したい事もあります。
その挑戦の後押しを是非皆さんの力を貸して頂き、背中を押してもらえるとありがたいです。
お忙しいところありがとうございました。